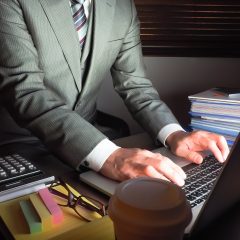給与を上げる「ベースアップ」と「定期昇給」その違いは?ベースアップの相場や計算方法もご紹介
従業員の給与を上げるときに、何を基準に上げればいいのか悩む人事担当者もいると思います。
今回は給与にかかわるベースアップと定期昇給の違いをご紹介いたします。またベースアップの相場や計算方法なども併せてご説明していきます。
人事担当者は、人事評価制度や給与制度の見直しを行う際の参考にしてください。

ベースアップとは
ベースアップは、従業員全体の基本給や賃金水準を上げることをいいます。和製英語で、ベアと略して使われることも多いです。
一般的にどの程度まで基本給を引き上げるのかは、景気の状態や物価の値動きなどを見て労働組合と使用者との交渉により決まります。
ベースアップには従業員の労働意欲の向上を図る働きがあり、高い生産性へとつながります。また企業の利益を従業員に還元するベースアップは、労働力が強まり、その結果再び企業に利益をもたらすという良いスパイラルを生み出すことができるのです。
定期昇給とは

ベースアップと混同しやすいのが「定期昇給」です。
給与が上がるという点ではベースアップと同じですが、定期昇給は年齢や勤続年数によって、定期的に基本給を上げる仕組みであり、昇給額は個人によって違います。
定期昇給は、企業の成績によっては行われなかったり、昇給したとしてもわずかな金額だったりすることもあります。このように給与がなかなか上がらないとなると、従業員の意欲は下がり同時に生産性も下がってしまいます。
そのため近年では、長らく日本の社会を支えてきた年功序列による定期昇給制度を廃止し、成果主義にシフトしていく動きが見られます。
ベースアップの相場

では、ベースアップの相場は一体どれぐらいであるのかを見ていきましょう。
経団連が発表した「2019年1~6月実施分 昇給・ベースアップ実施状況調査結果」によると、大手企業の昇給率は2.32%でした。また厚生労働省の「2019年賃金引上げ等の実態に関する調査」では、中小企業(従業員300人以下)の昇給率は1.9%でした。
しかし経団連が発表した「2020年・春季労使交渉最終結果」では、2020年の大手企業の昇給率は2.12%、中小企業で1.7%と前年比において下降しました。
また、東京商工リサーチが2020年7月20日に発表した「賃上げに関するアンケート」では、2020年度に賃上げを行った企業は57.5%にとどまり、2016年度以降で最大の下げ幅となりました。
2020年は新型コロナウイルス感染拡大が大きく影響し、社会全体として企業の大小に関わらず賃上げに大きなダメージをもたらしました。2021年春の労使交渉における賃上げについても、全体的にかなり厳しいことが予想されます。
ベースアップの計算方法

ベースアップの計算方法は「昇給前の給与×昇給率=昇給額」です。
例えば給与が20万円で昇給率が2%の場合は、「20万円×2%=4,000円」となり、ベースアップしたあとの基本給は20万4000円になります。
ベースアップでは、昇給額よりも昇給率に注目しましょう。昇給率は企業の成長の証しであり、今後の経営戦略を立てる指標にすることができます。また、中小企業であっても昇給率の上昇度をアピールすることで、今後の企業に対する期待を持たせ、多くの人材を集めることもできます。
まとめ

昨今の社会情勢をみると、どの企業も昇給が厳しくなることが予想されます。
しかし厳しい状況にあるのは企業だけではなく、従業員も同じです。企業の宝ともいえる従業員の労働意欲をこれ以上奪うことは、企業にとって大きなマイナスとなります。
2020年の春闘で7年振りにトヨタ自動車がベースアップを見送ったことは、大きな話題になりました。交渉は、年功序列制度を廃止し、成果主義を反映させる給与体制に変化させる方向性を示し労働組合の納得を得られました。
トヨタ自動車のベースアップ見送りの根拠にあるように、企業はベースアップを行うか否かに関わらず、ベースアップを含む従業員個々の昇給など賃上げ全般に対する明確な根拠を従業員に提示することが重要です。
経営状態や社会情勢が悪いからという理由だけではなく、成果を上げた従業員がしっかりと評価され、賃金に反映される人事評価制度の構築がこれからの課題となります。
(写真はACより)