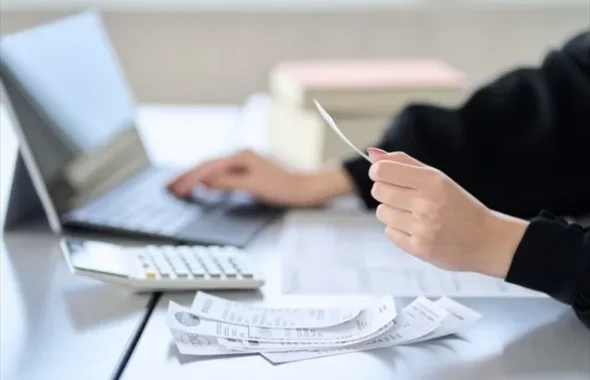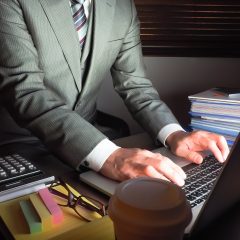時間を生み出す書類整理術|ひとり経理の効率化術
経理部門は見積書、請求書、領収書、契約書、納品伝票など、取引ごとに様々な書類を取り扱います。取引ごとに発生し、状況に応じて使い分けるこれらの書類は、一見似ていますが、取り違えたり紛失したりすると、重大な問題を引き起こす可能性もあるのです。また、書類を探したり、再発行したりするにも手間と時間が必要です。
ひとり経理にとってはこうした書類の整理整頓が、生産性を高める鍵となります。
本記事では、経理を担当する方々に効果的な、書類整理術を解説します。ぜひ参考にして取り入れてみてください。
書類の種類を基準に整理する
紙の書類を整理するには、まず分類別に分けることから始めます。書類をグループ化し、そのグループごとに保存すると探す手間が短縮できるのです。
1. 種類別の分類
書類を整理する際の基本は、種類別の分類です。
利用頻度が高い書類、例えば見積書や納品書などは、書類の種類ごとにフォルダを作って収納します。さらに、納品書フォルダの中ではインデックスなどを利用して、取引先ごとに分類しておくのも効果的です。また、納品書や請求書など月単位で使用するものは、月が変わったらひとつにまとめて保管場所へ移動するとよいでしょう。
利用頻度が低い書類、例えば社会保険や労働保険にかかわる書類などは「社会保険関係」「労働保険関係」など、ひとまとめのフォルダを作成して保管するのがおすすめです。
| 利用頻度 | 書類の種類 | 収納方法 |
|---|---|---|
| 高い書類 |
見積書 納品書 請求書 など |
・書類の種類ごとにフォルダを作って収納 ・インデックスなどを利用し、取引先ごとに分類しておく ・月が変わったらひとつにまとめて保管場所へ移動 |
| 低い書類 |
社会保険関係 労働保険関係 |
・フォルダを作ってひとつにまとめて保管 |
2. 時系列による整理
それぞれ分類の中で、書類を時系列順に並べるとさらに探しやすくなります。最新の書類を手前に、古い書類を奥に配置するのが一般的です。
また、経理書類には保管年数が決められているものがあります。例えば、帳簿や領収書、棚卸表などがそれにあたります。保存期間が定められている書類は、決算期で分けてひとまとめにして保管するとよいでしょう。10年保存の場合、このまとまりを10個分保管することになります。11年目には、最初に保管したまとまりの保管義務がなくなるため全て処分し、そこへ11年目の帳簿や書類を一式保管するのです。これをルーティーン化すれば、処分品を分類する手間が省け、整理しやすくなります。
デジタル化による効率的な管理
電子帳簿保存法の改正により、税務関係の帳簿や書類を電子データで保管することが認められました。決められたルールに従って、書類を保存することによって決算準備までスムーズにすすめられます。
電子帳簿保存法について詳しく知りたい方はこちら>>
「電子帳簿保存法について解説|経理初心者に教えるべき基礎知識」をご参照ください。
1. スキャンと電子保存
紙の書類をスキャンしてデジタル化すれば、保管スペースの節約だけでなく検索する手間も省けます。データの保管にはクラウドストレージがおすすめです。電子帳簿保存法に対応したサービスを利用すれば、タイムスタンプの付与といった法律の要件も満たせます。パソコンやメモリーへも保管できますが、デバイスが壊れてデータを確認出来なくなる可能性があるため、注意が必要です。
書類のデータ化は、電子帳簿保存法の要件と合わせて次の点に注意しましょう。
- 文字が読みやすいよう、高画質でスキャンする
- ファイル名をに日付と取引先名に変更する(例:20240716_取引先A_請求書.pdf)
- 訂正・削除履歴が残るシステムに保存をする
- 保存対象のファイルにタイムスタンプを付与する
2. 電子メールで届く請求書の管理
電子メールで届いた請求書は、電子帳簿保存法により紙での保存が認められません。必ずデータとして保管しましょう。次の4つの手順で管理すると効率的です。
- メールフォルダに請求書専用のフォルダを作成し、メールを自動で振り分ける
- 請求書の添付ファイルを、格納するフォルダに保存
- ファイルの名前を「取引年月日」「取引先」「取引金額」の3項目に変更
(例:2024年6月30日締め、山田商店からの15万円の請求書の場合
→ 20240630_yamadashouten_150000.pdf と変更) - 原本のメールは保管しておく(後日確認用)
3. オンラインショッピングの領収書管理
Amazonなど、オンラインショッピングサイトで発行される電子領収書も電子帳簿保存法上の電子取引です。令和6年以降は紙ではなくデータで保存しなければなりません。次の4ステップで管理するのがおすすめです。
- 購入時に領収書をPDFでダウンロード
- ファイルを「日付_ショッピングサイト名_商品名_金額.pdf」に変更
(例:2024年6月30日にAmazonで1000円のUSBメモリーを購入した場合 → 20240630_Amazon_USBmemory_1000.pdf と変更) - 決められたフォルダに保存
- エクセルで購入履歴一覧を作成し、領収書のファイル名とリンクさせる
定期的な整理と廃棄も重要
「たかが書類整理」と軽く考えがちですが、放っておくと書類の山はどんどん大きくなります。そうなると整理することが大仕事になり、取り掛かる気力も失われるのです。
そのため、書類の山は小さいうちに手をつけるのが賢明といえるでしょう。
1. 週次・月次の整理時間の確保
書類整理は小まめに行うのがコツです。週1回や月1回など、定期的に時間を決めて整理する習慣をつけましょう。
- 新しい書類を適切な場所に移動する
- 処理済み、未処理の確認と分類
- デジタル化が必要な書類のスキャン
- 不要になった書類の廃棄検査
2. 保存期間を考慮した廃棄
保存期間を考慮しつつ、定期的に不要な書類を廃棄することで、保管スペースを有効に活用できます。
- 法定保存期間を確認し、カレンダーに廃棄予定日を記入
- 機密情報を含む書類はシュレッダーで裁断
- デジタル文書を整理し、不要なものは削除する
まとめ
経理書類の効率的な管理方法を紹介しました。種類別の分類を軸に、時系列にまとめるとより検索性があがります。また、電子帳簿保存法の改正により、メールで受領した請求書や電子で発行された領収書は、紙での保管が認められなくなっている点に注意が必要です。
この記事で紹介した方法を参考に、自身の業務に合わせた書類整理のサイクルを構築してみてください。一度システムを確立したら終わりではなく、必要に応じて改善していくことも大切です。日々の整理方法を見直し、より効率的な方法を模索することで、時間の節約と業務品質の向上を実現しましょう。