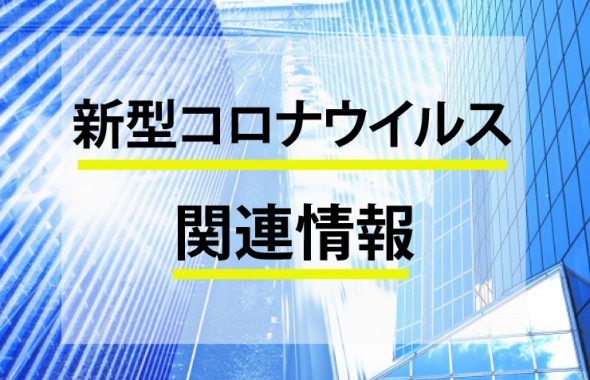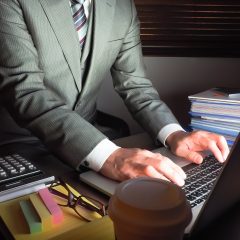【COVID-19】飲食店の生き残り戦略
期限付きでアルコールのテイクアウト販売が可能に
緊急事態宣言が解除となりましたが、営業時間の短縮・客席の削減対応等は続いており、飲食店にとっては厳しい状況となったままです。
イートインで減少した売上をカバーするために、テイクアウト販売をスタートした飲食店がありますが、酒類までテイクアウト販売しているところは少数です。
酒類のテイクアウト販売が不向きな飲食店もありますが、検討してみてはいかがでしょうか。
弊社のお客様で実際に酒類の販売を開始したお客様がいらっしゃるので、事例としてご紹介致します。
<客単価アップのためにアルコール販売を開始>
飲食店を経営されているお客様で、近隣の有名店と共同でお弁当のテイクアウトを始めました。お弁当の価格は1つ900円前後なので、客単価を上げるためにアルコールの販売も同時に始めました。
夕食用に家族分のお弁当を購入されるお客様が多いことから、晩酌用の需要を見込んでの事でした。価格は500円~1500円の幅で販売しています。
客単価アップのためにサラダなどの「プラス1品」を販売しているところもありますが、おかずやお弁当は種類を増やすと仕入れや容器、手間、そして売れ残りのリスクがあります。客単価アップの方法として、アルコールの同時販売はおススメできる方法です。
ただし、注意点があります。
仕入したものを販売できる免許のため、お酒のブレンド・果実を混ぜたものをテイクアウト販売すると、「無免許製造」の規定に抵触するため、こうした方法で酒類の提供等は出来ないそうです。
「カクテルセット」の様に、別々に販売して、自宅でブレンドできるセットを作るのも面白いかもしれません。
<アルコール販売を始めるのに必要な事>
通常、お酒のテイクアウト販売をするためには、「酒類小売業免許」が必要ですが、「料飲店等期限付酒類小売業免許」を取得すると、取得日から6ヶ月間テイクアウト販売が可能となります。
新型コロナウイルスの救済措置のため、申請期間は令和2年6月30日(火)までです。
「料飲店等期限付酒類小売業免許」で販売できる種類は、日本酒・ビール・焼酎・スピリッツ・リキュールなどすべての酒類が対象ですが、既存の在庫をはじめ既存の取引先からの仕入れの販売に限ります。
「量り売り」(購入者の希望する酒類を、希望する量だけ販売)や「詰め替え」(あらかじめ別の容器に小分けして販売)販売が可能であり、近隣からインターネットや電話での注文を受けて酒類を宅配することは可能です。しかし、インターネット等を利用して2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として酒類を販売することはできません(別途、通信販売酒類小売業免許を取得する必要があります)。
申請期限:令和2年6月30日(火)
免許期限:免許日から6か月
販売対象:既存の在庫をはじめ既存の取引先からの仕入れの販売に限る
※「料飲店等期限付酒類小売業免許」に登録免許税は課されません。●提出書類
〇申請時に提出が必要な書類
・酒類販売業免許申請書
・申請書 次葉1(販売場の敷地の状況)
・申請書 次葉2(建物等の配置図)
・住民票写し(法人については法人の登記事項証明書)
〇免許付与後に提出する書類
・申請書 次葉3(事業の概要)
・申請書 次葉6(「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書)
・酒類販売業免許の免許要件誓約書
・土地、建物、設備等が賃貸借の場合は賃貸借契約書等の写し、
その他契約書等の写し
・地方税(申請者が法人の場合は、「地方法人特別税」を含む。)の納税
証明書
・その他税務署長が必要と認めた書類
詳細は国税庁HPをご覧下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/menkyo/tebiki/kourigyou2016/index.htm