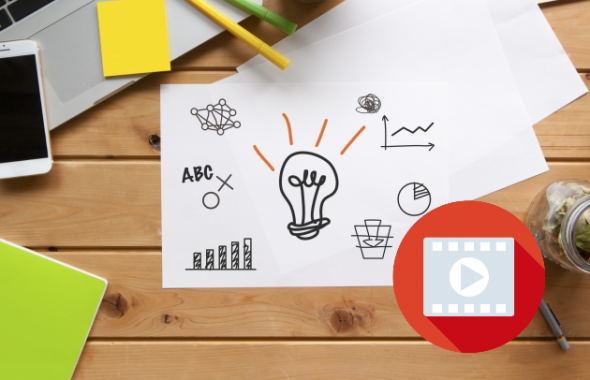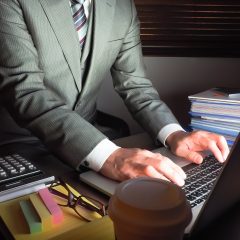社会福祉法人と特定収入(仕入控除税額の計算の特例)
社会福祉法人は、補助金、会費、寄附金等の対価性のない収入を財源として事業を行う場合があります。消費税法における仕入税額控除制度の性質上、このような対価性のない収入(特定収入)を原資とする課税仕入等に係る税額を課税売上に係る消費税額から控除することは合理的ではないと考えられていることから、仕入控除税額について調整を行う必要があります。
課税売上に係る消費税額-(仕入控除税額-特定収入に係る調整税額)=納付税額
【仕入控除税額の調整が必要な要件】
・簡易課税制度の適用を受けていない
・適格請求書発行事業者の税額控除に関する経過措置(2割特例)の適用を受けていない
・特定収入があり、特定収入割合が5%を超えている
【収入の区分】
まず、全ての収入取引を課税売上、非課税売上、不課税売上に分類します。
1.課税売上
国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、・貸付又は役務の提供を課税対象取引といい、このうち非課税売上を除いたものを課税売上といいます。
2.非課税売上
課税対象取引のうち消費に負担を求める税としての性格上課税の対象として馴染まないものや、社会政策的配慮により消費税を課すことが適当でないものについて、法律で非課税取引と定められている取引を非課税売上といいます。
3.不課税売上
収入取引のうち課税対象取引としての要件のいずれかを満たさない取引を不課税売上といいます。例えば、補助金収入、寄附金収入、借入金収入、内部取引による収入などが該当します。また、内部取引以外の全ての不課税売上は「特定収入」と「特定収入以外の収入」に区分されます。
【特定収入と特定収入以外の収入】
特定収入とは消費税法上、「特定収入に該当しない収入」に掲げる収入以外の収入をいうと定義されています。例えば次の収入が特定収入に該当します。
(1)補助金 (2)交付金 (3)寄附金 (4)出資に対する配当金 (5)保険金 (6)損害賠償金 (7)負担金 (8)国等からの繰入金 (9)会費等
解りやすく言うと、課税仕入に直接的又は間接的に使われるであろう不課税売上が特定収入であり、使途が非課税仕入・不課税仕入に限定される不課税売上が、特定収入以外の収入であると考えられます。
さらに特定収入を、その使途ごとに次のように区分します。
・課税売上対応課税仕入を使途とする特定収入
・共通対応課税仕入を使途とする特定収入
・非課税売上対応課税仕入を使途とする特定収入
・使途不特定の特定収入
分類の具体例
補助金・交付金以外の不課税売上は使途が特定されないものが多く、特定されない場合は使途不特定の特定収入となります。補助金・交付金ついては要綱等を確認し、使途が特定されるのか、特定される場合にはその使途が何なのかを確認します。
使途が特定されない→使途不特定の特定収入
使途が特定される→その使途が不課税・非課税仕入に特定(人件費補助金等)→特定収入以外の収入
使途が特定される→その使途が課税仕入に特定(資産の購入、費用)→使途特定の特定収入→対象事業により3つ(課税売上対応・共通売上対応・非課税売上対応)に分類
【特定収入がある場合の特定収入に係る課税仕入等の税額】
<個別対応方式の場合>
次の(1)+(2)+(3)の金額
(1)課税売上対応課税仕入等に使途が特定される特定収入の額×7.8/110
(2)共通売上対応課税仕入等に使途が特定される特定収入の額×7.8/110×課税売上割合
(3)(課税仕入等の税額の合計額-(1)の金額-(2)の金額)×調整割合
<一括比例配分方式の場合>
次の(1)+(2)の金額
(1)課税仕入等に係る特定収入の額×(7.8/110)×課税売上割合
(2)(課税仕入等の税額の合計額-(1)の金額)×調整割合
※調整割合=使途不特定の特定収入/(資産の譲渡等の対価の額+使途不特定の特定収入)
消費税確定申告後に地方公共団体より補助金に係る仕入控除税額報告書の提出を求められることがあります。特定収入割合が5%を超えなかった等の理由で仕入控除税額の調整が無かった場合には、補助金の一部返還を求められることがあります。その場合は報告書の手順に従い計算し、返還に応じてください。
会計や税務のことでお困りの社会福祉法人の皆様、コンパッソ税理士法人までお問い合わせください。
参考:国税庁パンフレット「国、地方公共団体や公共・公益法人等と消費税」
横浜青葉事務所 青木誠