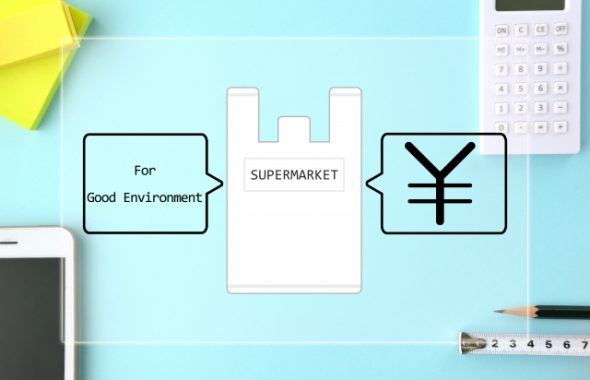「裁量労働制」を導入するときに必ず知っておきたい事
働いた時間ではなく成果で評価される裁量労働制
「みなし労働時間制」の1つである裁量労働制は、労働者が時間に縛られずに働ける制度ですが、導入している企業は少なく、日本にはまだ浸透していない印象です。
平成29年就労条件総合調査によると、「専門業務型裁量労働制」を導入している企業は全体の2.5%、「企画業務型裁量労働制」を導入している企業は全体の1.0%にとどまっています。
日本では、裁量労働制はなぜ導入が進んでいないのでしょうか。「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」は何が違うのでしょうか。今回は、この裁量労働制について掘り下げて見ていきます。

裁量労働制とは
裁量労働制は先述した通り、「みなし労働時間制」の1つで、労働者の裁量が大きい制度です。裁量労働制で契約し、みなし労働時間を8時間とした場合、3時間しか働かない日も12時間働いた日も8時間労働したとみなされます。
業務の遂行方法や労働時間は労働者自身が決めるため、会社が始業時間を指定したり、業務の遂行方法を具体的に指示したりする場合は法律違反とみなされる可能性があります。
原則、残業という考え方もありません。
「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」の違い
「裁量労働制」には、「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」の2種類あります。
「専門業務型裁量労働制」は、業務を行ううえでの手段や時間配分を、労働者の裁量に委ねる必要があると定められている業務にのみ適用されます。対象となる職種は公認会計士の業務、弁護士の業務、税理士の業務、中小企業診断士の業務など全部で19種類あり、厚生労働省令及び厚生労働省告示で定められています。
制度を導入するには、「制度の対象とする業務」や「労働時間としてみなす時間」、「業務遂行の手段や時間配分などを労働者に具体的に指示しないこと」などを明記した労使協定(36協定ともいう)を、所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。
協定の有効期間は3年以内とすることが望ましく、労働者の健康・福祉を確保するための具体的な措置や、苦情を受けたときの処理の手順や方法について明示しなければいけません
(参考:リーフレット「専門業務型裁量労働制」)。
一方、「企画業務型裁量労働制」は、事業の運営に大きな影響を及ぼす決定が行われる事業場にのみ適用されます。具体的には、本社や本店、本社の具体的な指示を受けずに事業計画を作成している支社などを指し、事業の企画や立案、調査、分析業務に就く労働者が対象になります。
導入手続きは「専門業務型裁量労働制」よりも複雑で、労働者の過半数以上で組織される「労使委員会」において、5分の4以上の賛成を得て決定した決議を、労働基準監督署に届け出なければいけません。
決議の有効期間は3年以内が推奨され、「専門業務型裁量労働制」と同様に、対象労働者の健康・福祉確保のための具体的な措置や、苦情を受けたときの対処法についても決めておかなければいけません(参考:リーフレット「企画業務型裁量労働制」)。
「裁量労働制」の残業と休日出勤の考え方
「裁量労働制」は、業務を遂行するうえでの時間配分が労働者に委ねられているので、原則、遅刻や残業という考え方はなく、残業代が発生することはありません。しかし、労働者の健康と福祉を確保するために、会社は勤務状況を把握しておかなければならず、勤務状況と健康状態を把握したうえで、代償休日や特別休暇を付与することが求められます。
また、業務上やむを得ず、休日出勤や深夜業が続く場合を考慮して、「専門業務型裁量労働制」導入時に締結する労使協定や、「企画業務型裁量労働制」導入時の労使委員会による決議において、割増賃金の支払い基準や、休日出勤や深夜業の恣意的な乱用を防ぐ具体的な方法などを決めておく必要があります。
「裁量労働制」と「フレックスタイム制」の違い
「裁量労働制」と似ている制度に「フレックスタイム制」があります。
「フレックスタイム制」は、「裁量労働制」と同様、始業時刻と終業時間を自分で自由に決めることができますが、会社が定めたコアタイムには必ず出勤していなければいけません。毎日決められた所定労働時間は働く必要がある点や、残業代が発生する点も「裁量労働制」と異なります。
「裁量労働制」と「フレックスタイム制」を混同しないように、正しく理解しておきましょう。
まとめ
「裁量労働制」には、「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」の2種類あり、それぞれ、対象となる業務が限定されています。日本での導入が進まない原因としては、業務が限定されていることや、導入時の手続きがやや煩雑なことなどが考えられます。
しかし、賢く活用することで、労働者、会社双方に大きなメリットがあります。労働者と相談を重ねたうえで、導入を検討してみてはいかがでしょうか。
(画像はphoto ACより)