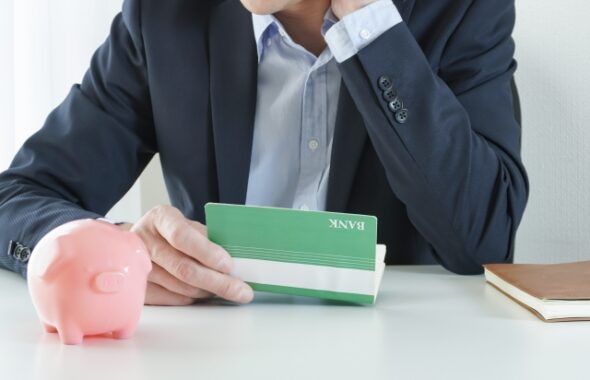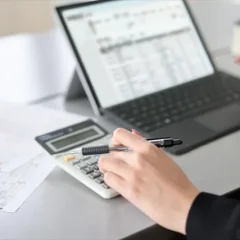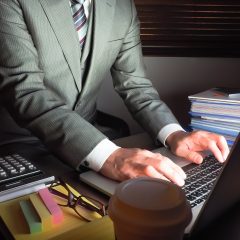デジタル遺産は生前に整理しておきましょう
総務省の令和5年通信利用動向調査によると、13歳~69歳の各年齢層でインターネットの利用率は9割を超えているとの結果がでており、ネット銀行や電子マネーなど、インターネットを利用した取引が急激に増加しています。
このようなネット上でしか確認できないデジタル遺産も故人の財産に含まれるため、金銭的価値のあるものは、相続財産として相続税の対象になります。
しかしながら、デジタル遺産は不動産などと違い現物がないため、相続人にとってその把握が難しく、相続時において問題となるケースが増えてきています。
1. デジタル遺産とは
デジタル遺産には法律上明確な定義はありませんが、一般的に故人がデジタル形式で保有していた財産を意味します。
例として次のような財産があげられます。
(1) ネット銀行やネット証券の口座
(2) 仮想通貨
(3) 電子マネー
(4) クレジットカード等のポイントやマイレージ
(5) デジタル形式の著作物 等
この他、財産的な価値はないものの、クラウド上のデータや写真の情報など、デジタル遺品と呼ばれるものもあります。
2. デジタル遺産の特徴と問題点
デジタル遺産はインターネット上で本人にしかわからない情報(ID、パスワード等)で保護、管理されています。
このため、相続人がその存在に気付かないことも多く、その結果、相続税の申告漏れや、サブスクの自動課金などで知らないうちに損失を被るなど、後にトラブルに発展することも考えられます。
また、その存在が分かったとしても、IDやパスワードがわからず、その内容の確認と解約などの手続きに相当の時間と労力を要する可能性があります。
仮想通貨や有価証券の相続税評価額は相続時点の価値になりますので、内容確認をしている間に価値が下がってしまい、相続税の支払いに窮することにもなりかねません。
3. デジタル遺産の生前対策
デジタル遺産は、何らの手掛かりもないなかで、その存在確認や解約の手続きを進めることは困難であるため、遺される方たちのためにも生前に整理しておくことが大切です。
生前整理のポイントは以下のとおりです。
(1) 利用しているデジタルサービスのうち不要なものは生前に解約しておく。
利用していないサービスは生前に解約しておくことで、余計な出費や相続人の手間を事前に減らしておけます。
(2) 利用しているサービスやスマートフォンのロック解除方法などを生前に親族に話しておく。
生前に相続人や親族に情報を伝えておくことで、相続時に財産調査がスムーズに行えます。
(3) エンディングノートや終活アプリ、遺言書等にデジタル遺産の情報(種類、ID、パスワード等)を記載し、家族が把握できるようにしておく。
デジタル遺産の情報を書き記しておくことで、相続時に要する財産調査の手間を減らせます。
(4) 死後事務委任契約によりデジタル遺産の整理を代理人に委任しておく。
死後事務委任契約とは、生前に死亡後の手続きを代理人に委託しておく契約で、デジタル遺産の整理の他、葬儀や行政手続きなど様々な事柄を委任しておくことができます。
代理人は友人や知人に依頼することもできますが、弁護士や司法書士などの専門家や信託銀行などの民間企業に委託することも可能です。
委任に要する費用は内容にもよりますが、50万~200万程度かかります。
渋谷事務所
土屋 和弘